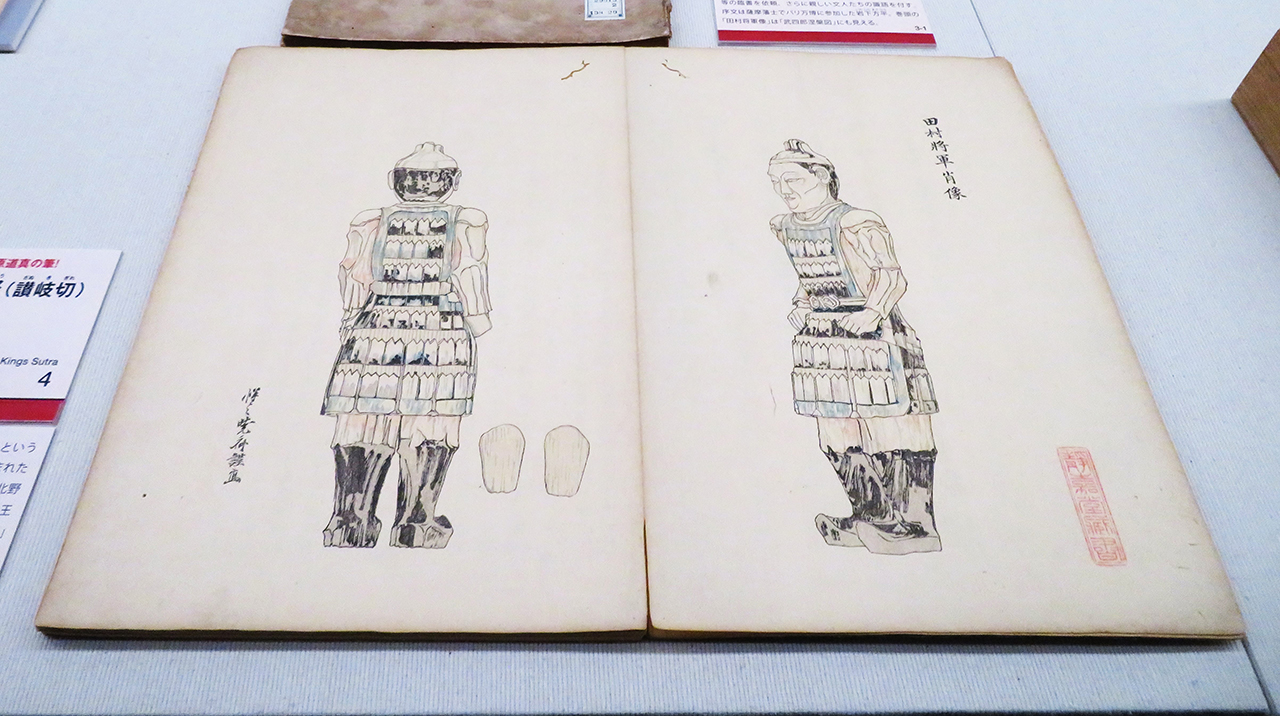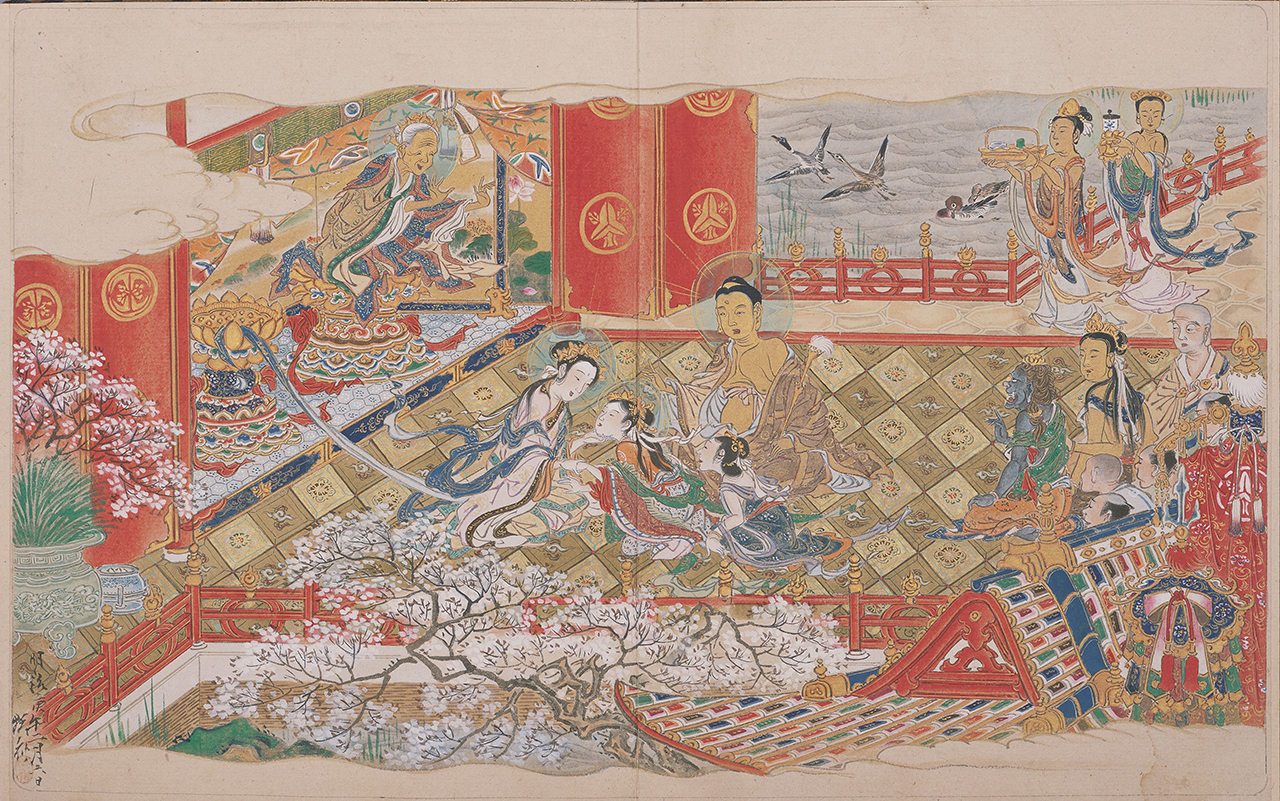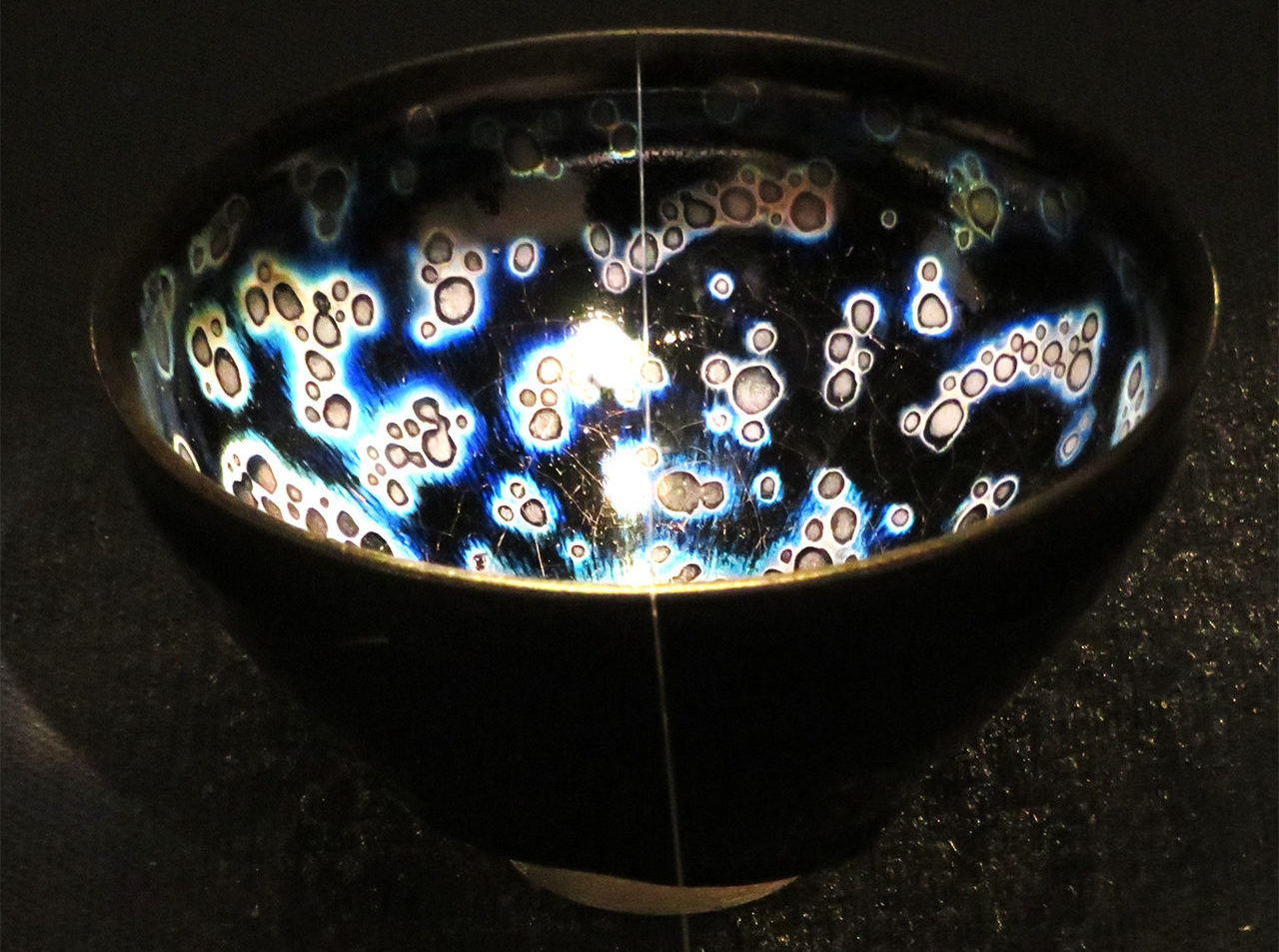美しいユートピア 理想の地を夢みた近代日本の群像
開催中〜2026/03/22
東京都・港区
マチュピチュ展
開催中〜2026/03/01
森アーツセンターギャラリー
東京都・港区
移転開館5周年記念 令和6年能登半島地震復興祈念 工芸と天気展 −石川県ゆかりの作家を中心に−
開催中〜2026/03/01
国立工芸館
石川県・金沢市
小出楢重 新しき油絵
開催中〜2026/03/01
東京都・府中市
開館30周年記念 ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン所蔵 ロックフェラー・コレクション花鳥版画展 北斎、広重を中心に
開催中〜2026/03/01
千葉県・千葉市
ガチャガチャ展in六本木
開催中〜2026/03/02
六本木ミュージアム
東京都・港区
セカイノコトワリ―私たちの時代の美術
開催中〜2026/03/08
京都府・京都市
デザインの先生
開催中〜2026/03/08
21_21 Design Sight
東京都・港区
名作展 源流へのまなざし モティーフで見る川端龍子
開催中〜2026/03/08
大田区立龍子記念館
東京都・大田区
開館30周年記念「ドナルド・キーン展 Seeds in the Heart」
開催中〜2026/03/08
世田谷文学館
東京都・世田谷区
ねり美・ふる文コラボ企画 もっと 浮世絵で行こ! 幕末明治の暮らし、娯楽、事件…
開催中〜2026/03/08
練馬区立石神井公園ふるさと文化館 2階企画展示室
東京都・練馬区
企画展「知覚の大霊廟をめざして――三上晴子の インタラクティヴ・インスタレーション」
開催中〜2026/03/08
NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
東京都・新宿区
ガウディ没後100 年公式事業NAKED meets ガウディ展
開催中〜2026/03/15
寺田倉庫G1
東京都・品川区
Artists in FAS 2025
開催中〜2026/03/15
藤沢市アートスペース
神奈川県・藤沢市
雛の世界
開催中〜2026/03/15
遠山記念館
埼玉県比企郡川島町
いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年
開催中〜2026/03/22
神奈川県・横浜市
横浜美術館コレクション展「子どもも、おとなも! つくるわたしが、つくられる」
開催中〜2026/03/22
神奈川県・横浜市
出光美術館所蔵 茶道具名品展
開催中〜2026/03/22
大倉集古館
東京都・港区
たたかう仏像
開催中〜2026/03/22
静嘉堂文庫美術館(東京・丸の内)
東京都・千代田区
没後40年 荻須高徳リトグラフ展 ―稲沢市荻須記念美術館コレクション―
開催中〜2026/03/22
八王子市夢美術館
東京都・八王子市
冬、そして春へー「華やぎ」と「侘(わ)び」の調(しらべ) 圏外の眼-伊奈英次の写真世界
開催中〜2026/03/22
荏原 畠山美術館
東京都・港区
向井山朋子 Act of Fire
開催中〜2026/03/22
アーツ前橋 ギャラリー
群馬県・前橋市
大西茂 写真と絵画
開催中〜2026/03/29
東京ステーションギャラリー
東京都・千代田区
劇場アニメ ルックバック展 —押山清高 線の感情
開催中〜2026/03/29
麻布台ヒルズ ギャラリー
東京都・港区
六本木クロッシング2025展:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠
開催中〜2026/03/29
東京都・港区
アジアの仏たち―永青文庫の東洋彫刻コレクション―
開催中〜2026/03/29
永青文庫
東京都・文京区
Tokyo Contemporary Art Award 2024-2026 受賞記念展「湿地」
開催中〜2026/03/29
東京都・江東区
北斎を魅了した天舞う瑞獣―龍・鳳凰―
開催中〜2026/03/29
北斎館
長野県・小布施町
VOCA展2026 現代美術の展望―新しい平面の作家たち
2026/03/14〜2026/03/29
上野の森美術館
東京都・台東区
北條正庸 風の旅
開催中〜2026/03/29
栃木県・宇都宮市
FACE展2026/絵画のゆくえ2026
2026/03/07〜2026/03/29
東京都・新宿区
高木由利子 写真展 Threads of Beauty 1995‐2025 ― 時をまとい、風をまとう。
2026/03/10〜2026/03/29
Bunkamuraザ・ミュージアム
東京都・渋谷区
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン展」
開催中〜2026/03/29
東京ドームシティ プリズムホール
東京都・文京区
英姿颯爽 根津美術館の武器・武具
開催中〜2026/03/29
東京都・港区
森重昭と被爆米兵調査-戦争が終わるということ
開催中〜2026/03/31
中央大学 法と正義の資料館
東京都・八王子市
ソル・ルウィット オープン・ストラクチャー
開催中〜2026/04/02
東京都・江東区
開館30周年記念 MOTコレクション マルチプル_セルフ・ポートレイト/中西夏之 池内晶子 —弓形とカテナリー
開催中〜2026/04/02
東京都・江東区
特別展 生誕151年からの鹿子木孟郎 —不倒の油画道
開催中〜2026/04/05
泉屋博古館東京
東京都・港区
開館20周年特別展 生誕1200年 歌仙 在原業平と伊勢物語
開催中〜2026/04/05
東京都・中央区
藤田嗣治 絵画と写真
開催中〜2026/04/12
茨城県近代美術館
茨城県・水戸市
東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき
開催中〜2026/04/12
東京都・台東区
ミュージアム コレクション特別篇 開館40周年記念 世田美のあしあと―暮らしと美術のあいだで
開催中〜2026/04/12
東京都・世田谷区
ミッション∞インフィニティ|宇宙+量子+芸術
開催中〜2026/05/06
東京都・江東区
飯川雄大 大事なことは何かを見つけたとき
2026/02/28〜2026/05/06
水戸芸術館 現代美術ギャラリー
茨城県・水戸市
特集展示「富士山 花と雲と湖と」
開催中〜2026/05/10
半蔵門ミュージアム
東京都・千代田区
下村観山展
2026/03/17〜2026/05/10
東京都・千代田区
春の江戸絵画まつり 長沢蘆雪
2026/03/14〜2026/05/10
東京都・府中市
生誕100周年記念 安野光雅展
2026/03/04〜2026/05/10
PLAY! MUSEUM
東京都・立川市
【特別展】 花・flower・華 2026 -横山大観の桜・川端龍子の牡丹・速水御舟の梅-
2026/02/28〜2026/05/10
東京都・渋谷区
コレクションの舞台裏 ―光をあてる、掘りおこす。収蔵品をめぐる7つの試み
開催中〜2026/05/10
埼玉県・さいたま市
テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート
開催中〜2026/05/11
東京都・港区
画布(キャンバス)に描くまなざし -ホキ美術館風景画展-
開催中〜2026/05/13
ホキ美術館
千葉県・千葉市
生誕100年記念「Re:辻邦生-いま、ふたたび作家に出会う」
2026/03/14〜2026/05/16
霞会館記念学習院ミュージアム
東京都・豊島区
福田尚代 あわいのほとり
開催中〜2026/05/17
神奈川県・鎌倉市
トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで
開催中〜2026/05/24
東京都・千代田区
モネ没後100年 クロード・モネ— 風景への問いかけ
開催中〜2026/05/24
東京都・中央区
カタリウム
開催中〜2026/05/24
東京都・中央区
SPRING わきあがる鼓動
開催中〜2026/05/31
神奈川県・足柄下郡箱根町
企画展「笑い滴る 春と夏の日本画名品選」
2026/02/25〜2026/05/31
松岡美術館
東京都・港区
企画展「内間安瑆・俊子展 色を織り、記憶を紡ぐ」
2026/03/07〜2026/05/31
神奈川県・三浦郡葉山町
W.ユージン・スミスとニューヨーク ロフトの時代
2026/03/17〜2026/06/07
東京都・目黒区
生誕100年 昭和を生きた画家 牧野邦夫 —その魂の召喚—
2026/03/31〜2026/06/07
茅ヶ崎市美術館
神奈川県・茅ヶ崎市
超危険生物展 科学で挑む生き物の本気
2026/03/14〜2026/06/14
東京都・台東区
軽井沢安東美術館 生誕140周年 藤田嗣治展
開催中〜2026/07/05
軽井沢安東美術館
長野県・軽井沢町
クヴェレ美術館 開館記念展Ⅰ Meet 美の交差点 近代日本画と東洋陶磁
開催中〜2026/07/05
クヴェレ美術館
茨城県・水戸市
ルネ・ラリックにみる 日本とフランスの“かわいい”文化交流
2026/03/20〜2026/12/06
箱根ラリック美術館
神奈川県・箱根町
![メスキータ
2019年、東京ステーションギャラリーにて日本で初めて開催された
「メスキータ」展の図録です。
オランダの版画家メスキータによる作品を掲載。「ハールレムの市庁舎」、「サボテン」、「ジャクリーン・ホンペルツの肖像」、「ファンタジー:さまざまな人々(黒い背景)」などをご覧いただけます。
表紙は「黒い寒冷紗」で包まれており、書籍コレクションとして垂涎の一冊です!
体裁の詳細はコチラをご参照ください。https://www.s-shiko.co.jp/design/mesquita/
[発行年月日]ー
[発行者]株式会社キュレイターズ
[状態]良いが、2辺に少々の反りアリ
[サイズ(mm)・ページ数]342×222×18 221ページ 表紙は布張り・ソフトカバー
[言語]日本語
※購入ご希望の方はメッセージにてお問い合わせください。
※送料はお届け先地域により変動しますので、お問い合わせください。
#芸術広場 #図録広場 #ミュージアムアンダンテ
#メスキータ展 #株式会社キュレイターズ #2019年](https://geijutsuhiroba.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)