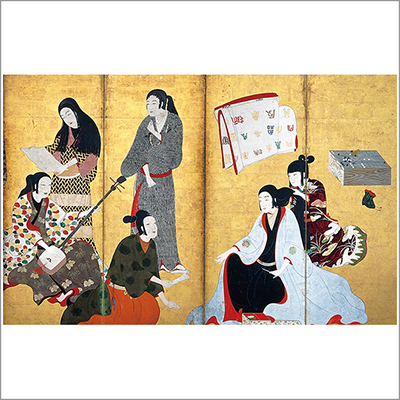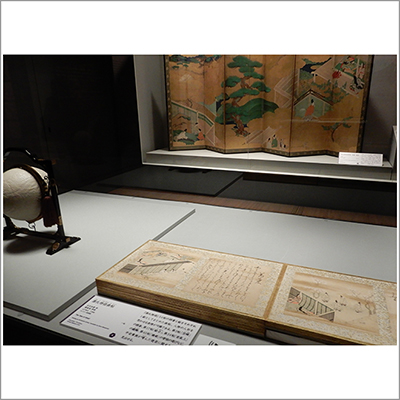国芳の団扇絵 ―猫と歌舞伎とチャキチャキ娘
開催中〜2024/07/28
太田記念美術館
東京都・渋谷区
美術の遊びとこころⅧ 五感であじわう日本の美術
開催中〜2024/09/01
東京都・中央区
「石川九楊大全」
開催中〜2024/07/28
上野の森美術館
東京都・台東区
カルティエと日本 半世紀のあゆみ 『結 MUSUBI』
開催中〜2024/07/28
東京都・台東区
トーキョーアーツアンドスペースレジデンス2024 成果発表展「微粒子の呼吸」第1期
開催中〜2024/08/04
トーキョーアーツアンドスペース本郷
東京都・文京区
倉俣史朗のデザイン―記憶のなかの小宇宙
開催中〜2024/08/18
京都府・京都市
おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展
開催中〜2024/08/18
国立工芸館
石川県・金沢市
新紙幣発行記念 北斎進化論
開催中〜2024/08/18
北斎館
長野県・小布施町
大川美術館コレクションによる20世紀アートセレクション ―ピカソ、ベン・シャーンからポップ・アートまで
開催中〜2024/08/18
栃木県・宇都宮市
生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界
開催中〜2024/08/25
東京都・港区
特別展「北斎 グレートウェーブ・インパクト —神奈川沖浪 裏の誕生と軌跡—」
開催中〜2024/08/25
すみだ北斎美術館
東京都・墨田区
TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション
開催中〜2024/08/25
東京都・千代田区
内藤コレクション 写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙
開催中〜2024/08/25
東京都・台東区
超・日本刀入門 revive―鎌倉時代 の名刀に学ぶ
開催中〜2024/08/25
静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館)
東京都・千代田区
「-没後100年-富岡鉄斎 鉄斎と文人書画の優品」(仮称)
開催中〜2024/08/25
山梨県・甲府市
デ・キリコ展
開催中〜2024/08/29
東京都・台東区
企画展「旅するピーナッツ。」
開催中〜2024/09/01
スヌーピーミュージアム
東京都・町田市
シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝
開催中〜2024/09/01
東京都・港区
AOMORI GOKAN アートフェス 2024 「つらなりのはらっぱ」
開催中〜2024/09/01
アートフェス(芸術祭)( 青森県立美術館、青森公立大学 国際芸術センター青森、弘前れんが倉庫美術館、八戸市美術館、十和田市現代美術館)
青森県
伊藤潤二展 誘惑
開催中〜2024/09/01
世田谷文学館
東京都・世田谷区
音を観る ―変化観音と観音変化身―
開催中〜2024/09/01
半蔵門ミュージアム
東京都・千代田区
111年目の中原淳一
開催中〜2024/09/01
東京都・渋谷区
エドワード・ゴーリーを巡る旅
開催中〜2024/09/01
神奈川県・横須賀市
ルーヴル美術館の銅版画展
開催中〜2024/09/01
八王子市夢美術館
東京都・八王子市
幻想のフラヌール―版画家たちの夢・現・幻
開催中〜2024/09/01
東京都・町田市
ザ・キャビンカンパニー 大絵本美術展〈童堂賛歌〉
開催中〜2024/09/01
神奈川県・平塚市
「ヨシタケシンスケ展かもしれない」
開催中〜2024/09/02
そごう美術館
神奈川県・横浜市
カルダー:そよぐ、感じる、日本
開催中〜2024/09/06
麻布台ヒルズ ギャラリー
東京都・港区
市制施行70周年記念 自然、生命、平和 私たちは見つめられている 吉田遠志展
開催中〜2024/09/06
東京都・府中市
日本のまんなかでアートをさけんでみる
開催中〜2024/09/08
原美術館ARC
群馬県・渋川市
企画展「未来のかけら 科学とデザインの実験室」
開催中〜2024/09/08
21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2
東京都・港区
特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」
開催中〜2024/09/08
東京都・台東区
須田国太郎の芸術――三つのまなざし
開催中〜2024/09/08
東京都・世田谷区
聖書の世界〜伝承と考古学〜/古代オリエントをたのしむ!子どもミュージアム
開催中〜2024/09/08
古代オリエント博物館
東京都・豊島区
慰問 銃後からのおくりもの
開催中〜2024/09/08
昭和館
東京都・千代田区
開館20周年記念 山梨放送開局70周年 平山郁夫 -仏教伝来と旅の軌跡
開催中〜2024/09/09
平山郁夫シルクロード美術館
山梨県・北杜市
霊気を彫り出す彫刻家 大森暁生展
開催中〜2024/09/16
群馬県・館林市
織田コレクション 北欧モダンデザインの名匠 ポール・ケアホルム展 時代を超えたミニマリズム
開催中〜2024/09/16
東京都・港区
トーキョーアーツアンドスペース レジデンス2024 成果発表展 『微粒子の呼吸』第2期
2024/08/17〜2024/09/22
トーキョーアーツアンドスペース本郷
東京都・文京区
フィロス・コレクション ロートレック展 時をつかむ線
開催中〜2024/09/23
東京都・新宿区
CLAMP展
開催中〜2024/09/23
東京都・港区
空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン
開催中〜2024/09/23
東京ステーションギャラリー
東京都・千代田区
吉田克朗展 ものに、風景に、世界に触れる
開催中〜2024/09/23
埼玉県・さいたま市
島袋道浩 : 音楽が聞こえてきた
開催中〜2024/09/23
BankART Station
神奈川県・横浜市
「人間×自然×技術=未来展(ひと かける しぜん かける ぎじゅつ は みらい てん) – Well-being for human & nature – 」
開催中〜2024/09/23
SusHi Tech Square内1F Space
東京都・千代田区
つくる展 TASKOファクトリーのひらめきをかたちに
開催中〜2024/09/23
茨城県近代美術館
茨城県・水戸市
和のあかり×百段階段2024 ~妖美なおとぎはなし~
開催中〜2024/09/23
ホテル雅叙園東京 東京都指定有形文化財「百段階段」
東京都・目黒区
平田晃久―人間の波打ちぎわ
2024/07/28〜2024/09/23
東京都・練馬区
【特別展】没後25年記念 東山魁夷と日本の夏
開催中〜2024/09/23
東京都・渋谷区
令和6年度夏季展「Come on! 九曜紋―見つけて楽しむ細川家の家紋―」
開催中〜2024/09/23
永青文庫
東京都・文京区
夏の特集展示2024「戦争の時代 日本における藤田嗣治 日常から戦時下へ」
開催中〜2024/09/24
軽井沢安東美術館
長野県・軽井沢町
印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵
開催中〜2024/09/29
東京富士美術館
東京都・八王子市
今森光彦 にっぽんの里山
開催中〜2024/09/29
東京都・目黒区
昭和モダーン モザイクのいろどり 板谷梅樹の世界
2024/08/31〜2024/09/29
泉屋博古館東京
東京都・港区
梅津庸一 クリスタルパレス
開催中〜2024/10/06
大阪府・大阪市
TOPコレクション 見ることの重奏
開催中〜2024/10/06
東京都・目黒区
大地に耳をすます 気配と手ざわり
開催中〜2024/10/09
東京都・台東区
レガシー ―美を受け継ぐ モディリアーニ、シャガール、ピカソ、フジタ
開催中〜2024/10/13
松岡美術館
東京都・港区
「空間と作品」
開催中〜2024/10/14
東京都・中央区
GO FOR KOGEI 2024「くらしと工芸、アートにおける哲学的なもの」
2024/09/14〜2024/10/20
富山県富山市/岩瀬エリア、石川県金沢市/東山エリア
富山県・富山市、石川県・金沢市
令和6年度第2期所蔵品展 「特集 新恵美佐子 祈りの花」
開催中〜2024/10/20
神奈川県・横須賀市
令和6年度第2期所蔵品展 特集:生誕100年 芥川紗織
開催中〜2024/10/20
神奈川県・横須賀市
彫刻の森美術館 開館55周年記念 舟越桂 森へ行く日
開催中〜2024/11/04
神奈川県・足柄下郡箱根町
北アルプス国際芸術祭 2024
2024/09/13〜2024/11/04
芸術祭(長野県大町市)
長野県・大町市
特別展「眼福―大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」
2024/09/10〜2024/11/04
静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館)
東京都・千代田区
瑛九 ―まなざしのその先に―
2024/09/14〜2024/11/04
神奈川県・横須賀市
MOTコレクション 竹林之七妍/特集展示 野村和弘/Eye to Eye-見ること
2024/08/03〜2024/11/10
東京都・江東区
ICC アニュアル 2024 とても近い遠さ
開催中〜2024/11/10
NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
東京都・新宿区
没後300年記念 英一蝶 ―風流才子、浮き世を写す―
2024/09/18〜2024/11/10
東京都・港区
日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション
2024/08/03〜2024/11/10
東京都・江東区
企画展「作家の視線― 過去と現在、そして…」
開催中〜2024/11/11
ホキ美術館
千葉県・千葉市
田名網敬一 記憶の冒険
2024/08/07〜2024/11/11
東京都・港区
特別展 文明の十字路 バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰 ―ガンダーラから日本へ―
2024/09/14〜2024/11/12
東京都・中央区
森の芸術祭 晴れの国・岡山
2024/09/28〜2024/11/24
芸術祭(岡山県北部12市町村、津山市、新見市、真庭市、鏡野町、奈義町など))
岡山県・北部12市町村
大正・昭和のモダニスト 蕗谷虹児展
2024/10/05〜2024/11/24
神奈川県・平塚市
フィリップ・パレーノ:この場所、あの空
開催中〜2024/12/01
神奈川県・足柄下郡箱根町
心象工芸展
2024/09/06〜2024/12/01
国立工芸館
石川県・金沢市
田中一村展 奄美の光 魂の絵画
2024/09/19〜2024/12/01
東京都・台東区
挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展『はにわ』
2024/10/16〜2024/12/08
東京都・台東区
ベル・エポック―美しき時代 パリに集った芸術家たち ワイズマン&マイケル コレクションを中心に
2024/10/05〜2024/12/15
東京都・港区
コスチュームジュエリー ―美の変革者たち― シャネル、ディオール、スキャパレッリ 小瀧千佐子コレクションより
2024/09/08〜2024/12/15
栃木県・宇都宮市
特別展 オタケ・インパクト ―越堂・竹坡・国観、尾竹三兄弟の日本画アナキズム―
2024/10/19〜2024/12/15
泉屋博古館東京
東京都・港区
ハニワと土偶の近代
2024/10/01〜2024/12/22
東京都・千代田区
西川勝人 静寂の響き
2024/09/14〜2025/01/26
千葉県・佐倉市
おしゃべり美術館 ひらビあーつま~れ10年記念展
2024/09/21〜2025/02/16
神奈川県・平塚市
![2018年、パナソニック 汐留ミュージアム(現:パナソニック汐留美術館)にて開催された「ジョルジュ・ブラック メタモルフォーシス」展の図録です。
キュビズムの創始者ジョルジュ・ブラックの作品を、初期の風景などの画業の変遷、造形上の変化をテーマに展示した展覧会でした。
晩年に取り組んだ「メタモルフォーシス」を日本で初めて本格的に紹介しています。
ページ数は少なめですが、掲載作品が多く楽しめます。
図録の構成は
・平面
・陶器
・ジュエリー
・朝貢
・室内装飾
掲載作品の一例
「青い鳥、ピカソへのオマージュ」,
「メディアの馬車」,「アレイオン」,
「ペリアスとネレウス」,「アケロオス」,
「トリプトレモス」,「セファレ」,
「ペルセポネ」,「小さなビリヤード台」
[発行年月日]ー
[発行者]ホワイトインターナショナル
[状態]良い
[サイズ(mm)・ページ数]210×135×8 90ページ
[言語]日本語
タグキーワード/2010~2020年代,絵画,版画,工芸,オブジェ,西洋美術,油彩,グワッシュ,リトグラフ,宝飾,陶器,モザイク,タペストリー](https://geijutsuhiroba.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)